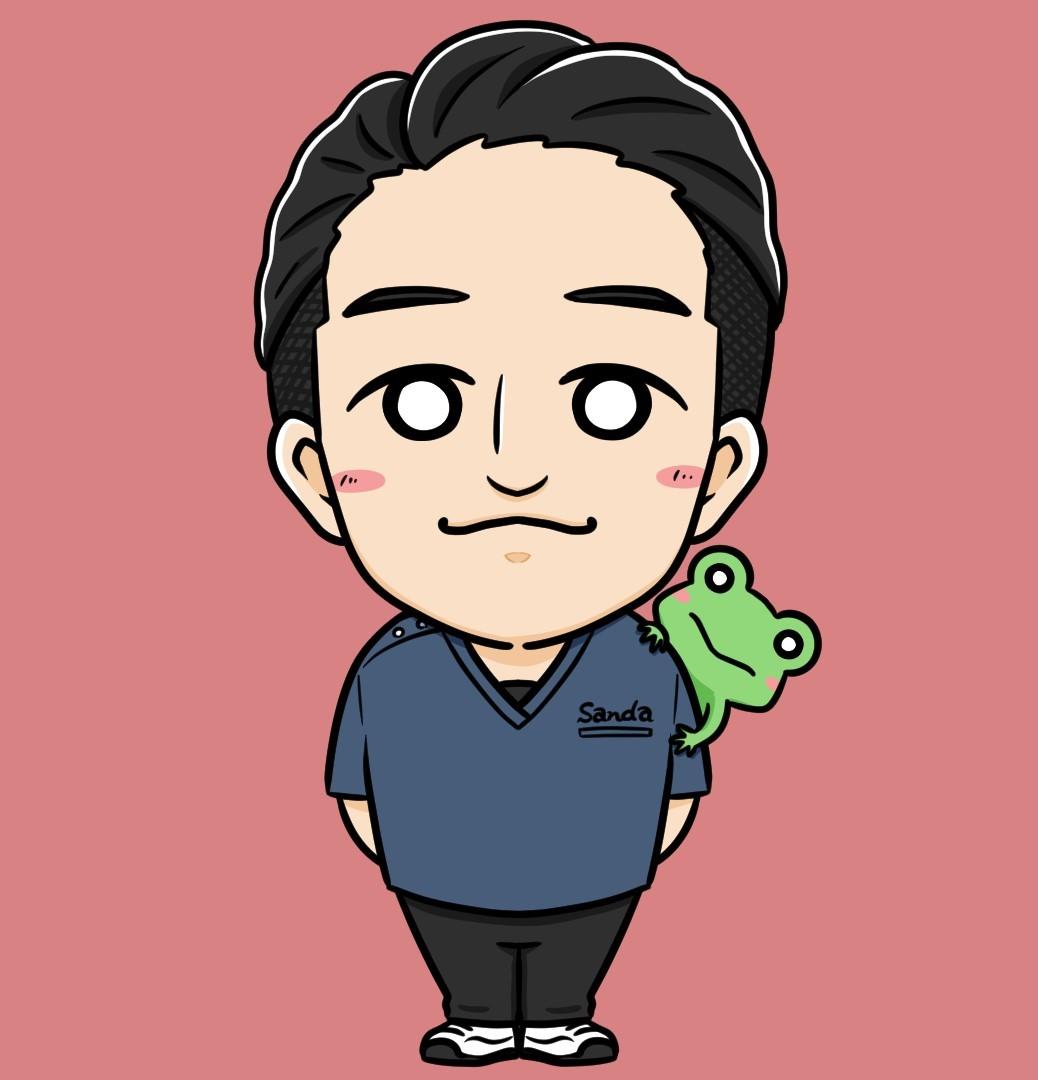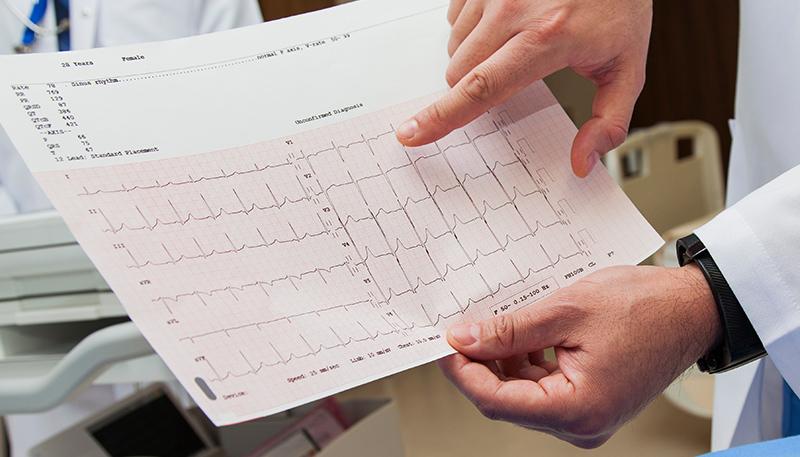少子高齢化、医療格差、医療費の増大など、医療や健康に関する社会課題は数多くあります。医療を提供するにあたって、こうした社会課題を考慮することは重要であり、国も解決を目指すための政策を打ち出してきました。
こうした医療・保健領域の政策だけでなく、あらゆる政策において"健康"を考慮するよう求めているのが「アデレード宣言」です。どのようなものなのか、概要や重要性、事例などを解説します。

執筆者:三田 大介
「アデレード宣言」とは
アデレード宣言(アデレード声明)は、2010年にオーストラリアのアデレードで提唱された、国際的な宣言です。WHO(世界保健機関)や南オーストラリア州政府を中心に、「全ての政策において健康を考慮すること(Health in All Policies)に関する国際会議」の参加者により作成されました。
"Health in All Policies"は、略して"HiAP"とも表記されます。
アデレード宣言のポイントは、大きく以下の2つに分けられます。
- 全ての部門が「健康と幸福」を政策展開の主要要素として取り込むことで、行政の目的が最もふさわしい形で達成されると強調する。その理由は、健康と幸福の根本は保健部門の範囲外にあり、社会的、経済的に形成されるためである。
すでに多くの部門が、人々の健康増進に貢献しているが、それでも大きな溝が複数存在する。 - アデレード声明では、人間開発、持続可能性と公平性を促進し、健康アウトカムを改善するために、全部門間での新しい社会契約が必要であることを概説している。そのためには、行政内で、全部門を横断して、あるいは行政の各階層間で協調したリーダーシップが存在する、新しい形態のガバナンスが求められる。本声明では、行政を横断する複雑な問題を解決する際の保健部門の貢献を強調する。
WHO「全ての政策において健康を考慮することに関するアデレード声明~健康と幸福のためにガバナンスを共有する方向へ~」p.1より引用(数字区分はドクタービジョン編集部加筆)
https://extranet.who.int/kobe_centre/sites/default/files/pdf/JA_Adelaide_Statement_on_Healthin_All_Policies.pdf
「1」では、医療・保健分野に限らず、あらゆる場面で行政が"健康"を意識することを提唱しています。
「2」では、行政にかかわるすべての部門が「健康と幸福」を政策の中心に置くことで、行政内を横断して課題解決を目指す必要性を強調しています。これまで国際機関をはじめ、国や自治体単位の多くの部門が、人々の健康増進を目標に取り組みを進めてきましたが、バラバラに動いていては最大限の効果を発揮できません。アデレード宣言はこの点を指摘しています。
健康との関連

そもそも"健康"とはどういった状態であるのか、WHO憲章から考えてみましょう。前文の一部(日本WHO協会訳)を以下に示します。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。
出典:公益社団法人日本WHO協会のwebサイト(2024年5月15日閲覧)
https://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/
この文章の後には、健康が基本的人権や世界の平和・安全にも必要であると続きます。つまり、健康はあらゆる社会課題と関連すると考えられていることがわかります。
WHO憲章の中では、健康に関する国の責任を明示しつつ、ほかの国との連携も強調しています。憲章の目標を達成するための共通基盤として、行政の羅針盤となるものがアデレード宣言と言えるでしょう。
健康の社会的決定要因(SDH)との関連
アデレード宣言は、「WHO健康の社会的決定要因に関する委員会」の2008年の報告書を活用しています。
健康の社会的決定要因(SDH:social determinants of health)とは、病気や健康の要因となる社会的な項目(要素)を示すものです。アデレード宣言はこの報告書に基づき、横断的な政策を行うことを提案しています。
「健康の社会的決定要因(SDH)」に関するWHO主要文書の邦訳||World Health Organization(WHO)
▼SDHに関する詳しい記事はこちら
SDH(健康の社会的決定要因)とは?医師が知っておきたいポイントを解説
SDGsとの関連
アデレード宣言は、単に"健康を何よりも優先せよ"というものではありません。先述のとおり、医療・保健分野以外にも焦点を当てています。これは、2015年に採択された持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)にも通じる考え方です。
SDGsでは、目標の3番目に「すべての人に健康と福祉を」が掲げられています。アデレード宣言はこの目標に直接関係するだけでなく、ほかのさまざまな目標を達成するためにも人々の健康が重要である、という考えを提唱するものです。
また、目標1の「貧困」や10の「不平等」など、格差をなくすことで健康や幸福が向上する、といった相互作用もあるでしょう。
人々の健康・幸福と、さまざまな社会課題の間に好循環を生み出すには、行政部門の連携・協調が必要なのです。
全ての政策において健康を考慮する(Health in All Policies)アプローチ

実は、Health in All Policies(HiAP)というアプローチは、アデレード宣言が出される前から多くの国で試されてきました。
アデレード宣言ではそうした成果をふまえ、有用とされる手段をいくつか紹介しています。たとえば、多部門で構成される委員会やチーム、分野横断的な情報システムなどです。
こうした仕組みは国や自治体の指導者・政策立案者が健康・幸福について考える一助になると示しています。
協調した行政の必要性と例
「協調した行政」の活動例として、アデレード宣言では以下のような取り組みを紹介しています。
経済と雇用
経済成長は、人々が健康であることが前提となります。健康であるほど家計も豊かになり、より生産的に働くこともできます。
また、安定した雇用が保障されることで、人々を健康に導くことができます。
教育
子どもやその家族が健康でないと、学業に悪影響を及ぼす恐れがあります。十分な学びによってさらに健康が向上し、生産的に社会に参加することもできます。
インフラ関係
交通や住宅などを検討する際、健康への影響を考慮することで、環境負荷や人・モノ・サービスの移動効率を改善できます。
保健部門が果たす新たな役割
すべての政策で健康を考慮するには、保健部門との連携が重要です。それもただ連携すれば良いだけではなく、保健部門が外部に対して提供できる十分な情報や権限を備えている必要があります。
アデレード宣言では、保健部門の責務として、他部門が抱える課題や行政義務への理解、戦略のエビデンス構築、健康効果の評価などを示しています。
医療従事者の中では、社会医学系専門医や保健師が活躍することになりそうです。
社会医学系専門医とは?資格の必要性や業務内容、制度や働き方を紹介
医師はアデレード宣言をどう意識すれば良いか
医療というシステムは社会の中に包括されているため、必ずと言って良いほど政策の影響を受けます。
医療費適正化計画や「健康日本21」、地域医療構想など、医療・保健分野に直結するものはイメージしやすいと思いますが、他分野の政策にも目を向けてみると、たとえば地方創生や経済発展、国際協力の分野は、その地域に住む人々の健康が前提になっており、先述したような相互作用によっても政策が進行する良い例に思えます。男女共同参画などは、性差医療の観点も重要になるでしょう。
アデレード宣言が出た/知ったからと言って、私たちの日々の臨床業務が大きく変わるわけではありませんし、変える必要もないでしょう。しかし、病気を治すことだけが責務であるという考え方でもいけません。患者さんが「健康・幸福」でいられることが重要であり、そのためのサポートのために国や世界の動向を知っておく必要があると考えます。
ちなみにアデレード宣言やHiAPの知識は現在、医師国家試験でも出題され得る内容です(令和6年度版医師国家試験出題基準から掲載)。「全ての政策において健康を考慮すること」の意義を医師に知っておいてほしいことの表れでしょう。
医師国家試験出題基準(令和6年版)|厚生労働省
▼関連記事はこちら
医療費適正化計画とは?―第四期【2024~2029年度】の内容を中心に解説
「健康日本21」とは?2024年度に始まる第三次目標についても解説
地域医療構想の現状は?2025年以降の取り組みについても解説
性差医療とは?医師が知っておきたい概要や具体例、問題点などを解説
まとめ
今回はアデレード宣言について紹介しました。一見医療保健と関係がなさそうな政策でも健康が考慮されるようになると、社会情勢が健康に与える影響が大きくなっていくとも言えます。臨床業務の中で実感することは多くはないかもしれませんが、医療の担い手として国や世界がどのように動いていくのかには、今後も注視していきたいですね。