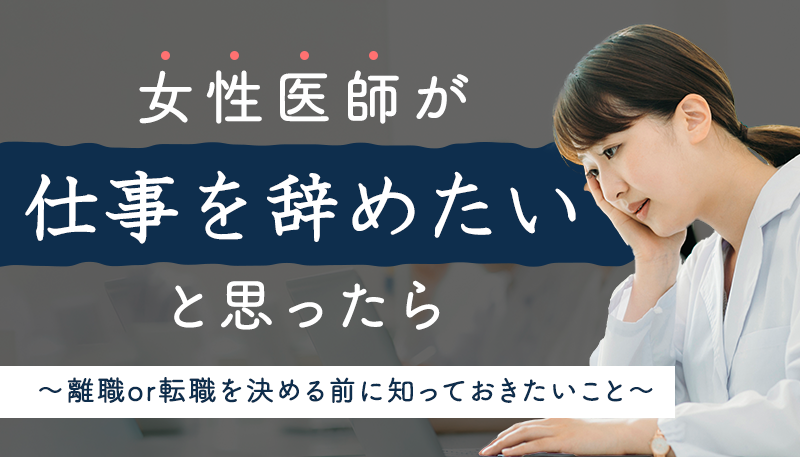「研修登録医」という名称を聞いたことはあるでしょうか。簡単に言うと、医師が大学病院で生涯学習を行うために設けられた制度です。最近は"大人の学び直し"として「リスキリング」や「リカレント教育」といった言葉を耳にする機会が増えましたが、研修登録医制度は私たち医師における"学び直し制度"の一つとも言えるでしょう。
この記事では研修登録医についての概要や、研修登録医になるための条件、制度を利用するメリットなどを解説します。ぜひ最後までご覧ください。

執筆者:Dr.SoS
研修登録医とは
「研修登録医」とは、大学病院で医学や医療に関する研修を受ける医師を指します。
医師免許取得から2年以上が経過し、診療所や病院に勤務している医師が該当しますので、"研修"という言葉が付いていますが研修医や専攻医(後期研修医)とは関係がない点に注意しましょう。
研修登録医制度の概要
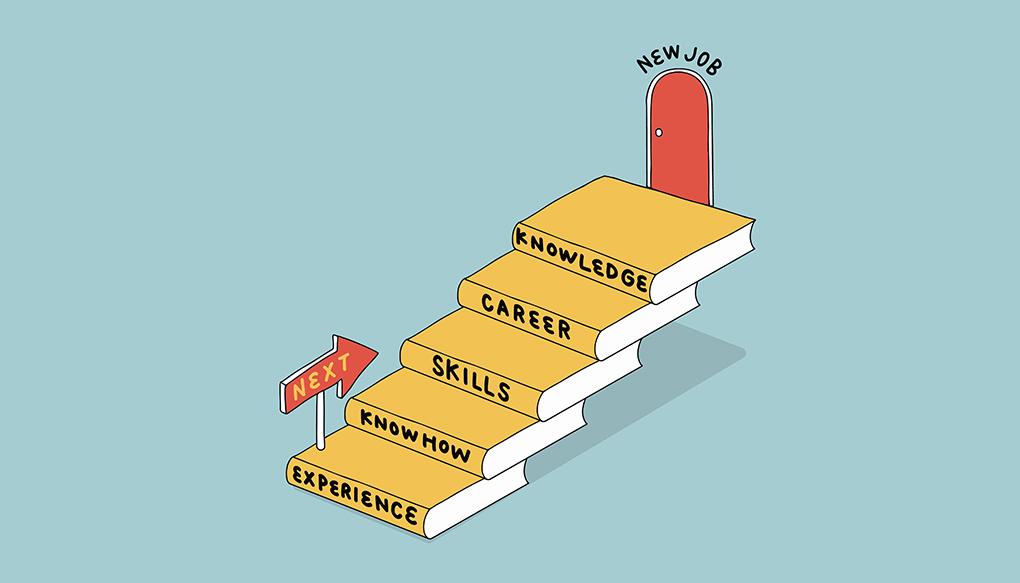
まずは、研修登録医に関する制度について見ていきましょう。
研修登録医制度は、医師の生涯学習を促進するための制度です。大学病院が地域の病院や診療所などと連携し、地域医療の発展に寄与することを目的に、1989(平成元)年8月に導入されました。比較的歴史の長い取り組みではありますが、医師の間でもそれほど知られていないのではないでしょうか。
研修先は主に大学病院で、研修は基本的に1年単位で実施されます。下記のような診療や研究に参加することができます。
| 臨床研修 | 各診療科の専門医の指導の下、実際の診療に参加し、臨床経験を積む |
|---|---|
| 症例検討 | 難症例に関して専門家を交えてディスカッションを行い、問題解決へのアプローチや具体的な解決手順を学ぶ |
| 臨床研究 | 診断推論の総論について学ぶ |
プログラム期間は研修先によって異なりますが、1カ月や3カ月など、月単位で受け入れている医療機関が多くなっています。プログラム内容も一律ではないため、研修希望者の日程に合わせて、ある程度柔軟に対応してもらえるでしょう。
ここで注目したいのは、研修登録医制度を利用する場合はこれまでのキャリアパスとは異なる診療科が選択されることが多い点です。たとえば下記のようなケースがあります。
- これまで臓器別診療を専門としていた医師が、開業を前に一通りのコモンディジーズへの対応力を身に付ける
- 西洋医学のみで対応困難な症状に対する治療選択肢として漢方診療を学ぶ
医師は、臨床研修から時間が経つほど「自分の専門診療科以外のことはよくわからない」という状況になりがちです。医師が生涯専門性を磨くための教育制度だけでなく、長年スペシャリストとして活躍してきた医師が専門外の診療にも携わりたいと思ったときに、それをサポートするような教育体制もあることが望ましいでしょう。こうした場面で活用が想定されているのが「研修登録医制度」と言えます。
研修登録医になるには

研修登録医になるためには、医師免許(または歯科医師免許)取得後2年以上経過していることが条件です。つまり、基本的には臨床研修(初期研修)を修了していることが必要となります。
加えて、所属する医療機関長医師会/歯科医師会会長の推薦も必要です。
また、研修料として月額6,000円程度を前納することが一般的です。必要な書類を準備した上で、希望する大学病院・医療機関の研修担当部署に申請します。
実際は各研修先の研修・教育内容は千差万別ですから、申請を出す前に一度アポイントメントを取って、どのような教育が受けられるか尋ねてみるのが良いでしょう。あまり多くはないかもしれませんが、身近に研修登録医制度を活用した医師がいれば、話を聞くことで有益な情報が得られるでしょう。
研修登録医制度を活用するメリット

研修登録医になることで得られるメリットには、下記のような点が考えられます。
- 最新の医学知識・技術の習得:最新の医療に触れることで、知識や技術をアップデートし人材価値を高めることができる
- 専門医との交流:大学病院等の現役専門医との交流を通して、臨床経験や研究に関するアドバイスを受けたり、人的ネットワークを広げたりすることができる
- 地域医療への貢献:学んだ知識や技術を地域医療に還元することができる
医学の発展で分野や疾患が細分化されたことで、診断や治療方法は日々、新たな選択肢が増えていっています。高度に専門分化した世界では、広く浅く能力を高めるよりも、自身の専門分野に特化しスキルを高める戦略が効率的です。
このため多くの医師は、臨床研修後すぐに臓器別診療科(循環器内科、消化器内科、整形外科など)へ進み、その科でスキルアップをはかることで専門性の高い医療を提供します(以前は大学卒業後すぐに専門診療科に進んでいましたが、基本的な診療能力が十分に取得できないという弊害も生じたため、2004(平成16)年に臨床研修が必修化されました)。
2年間の臨床研修で幅広い分野の診療を学ぶとはいえ、その後は専門分化した道に進むため、先述のとおり、研修から時間が経つほど「自身の専門診療科以外のことはよくわからない」という状況になりがちです。自身の専門診療科以外の知識を学ぶには、研修登録医制度の活用が一つの選択肢となります。
ちなみに日本内科学会では、長年スペシャリストとして活躍してきた医師が専門領域外の診療を学ぶための「リカレント教育」の必要性が認識されており、体制や学習コンテンツを整備するためのワーキンググループも発足しています。今後はこのような学会ごとの取り組みも普及していくのかもしれません。
キャリア形成においては、"掛け算"が有効とされます。たとえば、ある特定の分野で"1万人に1人"の存在になるのは難しいですが、もし"100人に1人"の存在になることができれば、それを2つ掛け合わせて"1万人に1人"の存在を目指せます。研修登録医制度を活用して、これまでと異なる分野の学びを深めることは、掛け算式で医師としての人材価値を高めるためにも有益と考えられます。
昨今は「人生100年時代」と言われるようになり、一般社会では一つの組織にとらわれず、転職や独立開業、副業などが一般的となりました。医療業界においても"学び直し"を通して自身の人材価値を高めることが、ますます重要視されるようになるでしょう。
内科医リカレント教育セミナー|日本内科学会
リカレント教育コンテンツ タッチ&トライ(全14コンテンツ)|日本内科学会
▼関連記事はこちら
医師の副業について現役医師が解説。自分らしく働く上でおすすめの仕事や注意点とは
医師の起業(ビジネス起業)増加の背景とは|起業事例と起業する際のポイント
研修登録医のモデル事例
実際に研修登録医制度を利用した事例としては、これまで西洋医学を中心に研修を行っていた医師が漢方医療を学ぶことで診療の幅を広げられた例や、出産や育児によるブランクがあった医師が臨床現場へ復帰する前にプログラムを利用して研鑽を積んだ例などがあります。
できれば研修登録医制度を利用した医師の生の声を直接聞けると良いですが、各病院の公式サイトで実例やインタビューなどが掲載されている場合もありますので、目を通してみると良いでしょう。
まとめ
研修登録医制度は比較的歴史が長い取り組みですが、あまり知られていない印象があります。医師はこの制度を活用することで、専門性の高い分野の理解を深めることができるでしょう。とくに出産や育児などを機に医療現場から離れ、すぐの復帰が難しい人や、これまでと異なる分野で研鑽を積みたい人には意義のある制度かと思います。気になる方は各施設へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
この記事が研修登録医制度への理解を深め、利用するきっかけの一つになれば幸いです。
名古屋大学医学部附属病院研修登録医受入れ規程|東海国立大学機構規則集
臨床再研修プログラム(復職・転職支援)|名古屋大学医学部附属病院 総合診療科
出産・育児によるブランクからの復職|名古屋大学医学部附属病院 総合診療科
研修登録医|千葉大学大学院医学研究院 診断推論学・千葉大学病院 総合診療科
生涯学習(研修登録医)について|千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学
大阪大学研修登録医受入れ規程|大阪大学
研修登録医|九州大学病院 臨床教育研修センター
研修登録医・病院研修生・受託実習生の申込み|東北大学病院
※URLは各大学のサイト利用規約等に従い掲載しています。