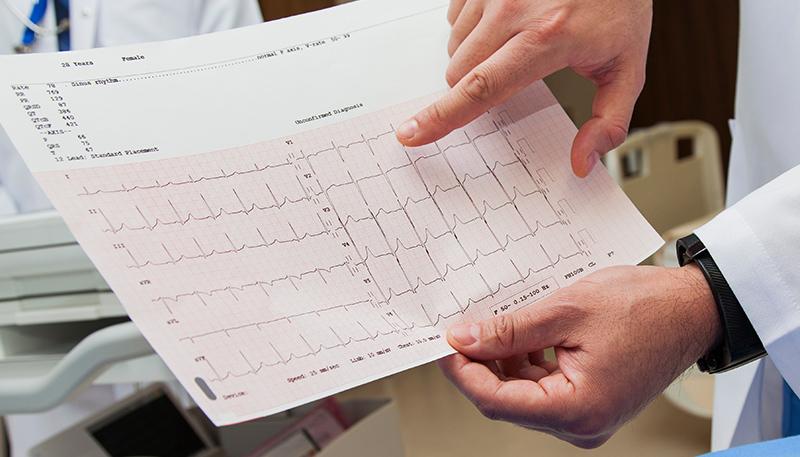医師であれば誰しも一度はかかわり得る「耐性菌」。近年、世界的に耐性菌のまん延・拡散が問題視されており、このままいけばいずれ抗菌薬が効かない"耐性菌ばかりの世界になる"とも危惧されます。
我々医師が、なぜ細菌が薬剤耐性を獲得するのかを改めて理解し、適切に抗菌薬などの薬剤を取り扱えば、将来の景色を変えられる可能性が高いと言えます。
この記事では耐性菌の概要や原因、現状や今後の対策について解説します。

執筆者:中山 博介
耐性菌とは
耐性菌(薬剤耐性菌)とは、1つ以上の抗菌薬に対して薬剤耐性(AMR:antimicrobial resistance)を獲得し、その薬剤に対する抵抗力が高く、薬が効かない状態に変化した細菌のことです。
厄介なことに、AMRは耐性を持たない別の細菌にも伝達されます。その細菌もAMRを獲得し、次々に連鎖していくことがあります。
「AMRの原因は抗菌薬にある」と考える医師も少なくありませんが、耐性菌は北極の永久凍土からも発見されています。もともとAMRを持っている細菌が存在するためで、抗菌薬が登場するはるか昔から耐性菌自体は存在しているのです。
一方で、抗菌薬が耐性菌の流行や多剤耐性化に拍車をかけたことは間違いありません。1940年代、ペニシリンをはじめとする抗菌薬の普及をきっかけに、耐性菌も世界中で急速に出現・拡散しました。
それ以降、新たな抗菌薬の誕生に追従するかのように、細菌は次から次へと、さまざまな抗菌薬に対してAMRを獲得していきました。
1993年、当時の耐性菌に対する"最終兵器"だった「カルバペネム系抗菌薬」にも耐性菌が発見されます。カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE:carbapenem-resistant Enterobacterales)です。CREにより髄膜炎や肺炎などの重篤な感染症を発症した場合、治療の選択肢は少なく、死亡率は非常に高いことが報告されています。
こうした新規耐性菌の発生・拡散に対して、世界保健機構(WHO)は世界中で取り組むべき課題として警鐘を鳴らしています。
国内の管理状況

日本では現在、国内で問題となる耐性菌感染症を、すべての発症患者について報告を求める「全数把握対象疾患」と、定められた医療機関からのみ発症患者の報告を受ける「定点把握対象疾患」に分けて管理しています。
| 【全数把握対象疾患に分類される感染症】 |
|---|
|
| 【定点把握対象疾患に分類される感染症】 |
|---|
|
出典:東京都感染症情報センターwebサイト「薬剤耐性菌関連情報」
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/resistant/(2024年6月13日閲覧)
ほかにも、多剤耐性緑膿菌(MDRP)やセラチア菌、ESBL産生菌など、多くの耐性菌が臨床の場で問題となっています。
耐性菌ができる原因やメカニズム
先述したように、初めからなんらかの抗菌薬に対して自然耐性を持つ細菌もありますが、昨今の問題は抗菌薬が効いていた細菌がAMRを獲得してしまうことです。
では、どのようにして細菌はAMRを獲得し、耐性菌となってしまうのでしょうか。細菌がAMRを獲得するメカニズムは主に下記の5つです。
①細菌外膜の変化(透過性低下)
②抗菌薬の排出(エフラックスポンプの機能亢進)
③抗菌薬の標的部位の変化(DNA・RNA変異)
④抗菌薬の不活化(βラクタマーゼ産生など)
⑤バイオフィルムの形成
抗菌薬は細菌外膜に存在する小さな孔から細菌内に侵入し、それぞれがターゲットとする標的部位を攻撃することで細菌を破壊します。
そこで、細菌は外膜の透過性を低下(①)させたり、同じ細菌同士でバイオフィルムと呼ばれる集合体を形成(⑤)したりすることで、抗菌薬の侵入を防ぐよう変化します。
細菌内に侵入してきた抗菌薬に対しては、細菌外に排出するエフラックスポンプの機能を亢進(②)させたり、抗菌薬の標的部位を変異(③)させる、もしくはβラクタム系抗菌薬を加水分解する酵素「βラクタマーゼ」を細菌内で産生(④)させたりすることで、自身を守ろうと変化するわけです。
たとえば、実臨床でよく目にするMRSAは、ペニシリン系抗菌薬の標的部位である「ペニシリン結合タンパク」(PBP)を遺伝子変異させた細菌です。ほかにも、広範囲なβラクタム系抗菌薬を分解できるβラクタマーゼ、いわゆるESBL(extended spectrum beta-lactamase)を産生する大腸菌(ESWL産生菌)などの増加も問題視されています。
抗菌薬の不適正使用

上記のようなメカニズムで耐性菌が発生しても、通常体内には耐性菌以外の多種多様な細菌(常在菌)も存在しており、お互いにバランスを保ちながら一つの"社会"を形成しています。
実臨床で問題となるのは、ヒトの体内で耐性菌だけが大量に繁殖し、なんらかの感染症を引き起こすことです。
耐性菌が大量に繁殖する理由の一つに、抗菌薬の不適正使用があります。耐性菌以外の菌が減少し、耐性菌だけが繁殖しやすい環境が体内で形成されてしまうためです。とくに広域な抗菌薬ほど、それだけ多種多様な常在菌を減少させるため、生き残った耐性菌が繁殖しやすくなります。
不十分な投与量・期間で抗菌薬を使用した場合も、正しく使用していれば減らせたはずの耐性菌が生き残り、ほかの弱い菌はいなくなるため、耐性菌が繁殖しやすくなります。
耐性菌の繁殖を食い止めるには、抗菌薬の適正使用が重要なのです。
【医療従事者の方へ】薬剤耐性が拡大する要因|AMR 臨床リファレンスセンター
【医療従事者の方へ】抗菌薬の適正使用について|AMR 臨床リファレンスセンター
【一般の方へ】不適切な処方・不適切な服用|AMR 臨床リファレンスセンター
耐性菌に対する治療や対策
これ以上耐性菌がまん延すれば、抗菌薬が効かない、つまり抗菌薬の存在しなかった時代の医療に戻ってしまうのではと、国際社会でも懸念する声があがっています。
ここでは、耐性菌の現況と、近年実施されている治療や対策を紹介します。
2050年、AMRはさらに悪化する?
WHOの報告によれば、2013年のAMRに起因する世界での死亡者数は低く見積もって70万人でした。しかし、何も対策せずにこのままのペースで耐性菌がまん延した場合、2050年には死亡者数が1,000万人以上にのぼると想定されています*1。
これは、現在のがんによる死亡者数を超える数値です。経済的損失も計り知れません。
とくに日本では、広域抗菌薬であるセファロスポリン・キノロン・マクロライド系抗菌薬の使用割合がきわめて高いことが知られており、MRSA感染症やPRSP感染症の検出割合は世界でもトップクラスです。
今後、少子高齢化がさらに進むことが予想されるため、我々医師は免疫能力の低い高齢者への影響をより考える必要があり、今のうちから適切な治療や対策を施すことが重要です。
新薬開発の現状と展望
耐性菌に対する治療をするには、耐性を持たないほかの抗菌薬を使うか、新たな抗菌薬を開発するしかありません。
開発に関しては、1929年に発表されたペニシリンから始まり現在に至るまで、多くの抗菌薬が生み出されてきました。1980年から1990年代前半までに開発されたセフェム系抗菌薬の約70%、キノロン系抗菌薬の約75%は日本の製薬会社によって作られたといい*2、日本は世界の抗菌薬開発を牽引してきたと言えます。
しかし、開発が進み多種多様な抗菌薬にあふれた結果、耐性菌が急増し、新規抗菌薬の開発にも陰りが見え始めます。事業の収益性の低さや技術的な課題などから、世界的にも開発が停滞したのです。
こうした状況をふまえ、WHOは2015年、世界各国にAMRの対策アクションプランの作成を提言しました。欧米諸国を中心に、日本でも厚生労働省がアクションプランを策定しています(後述)。
対策アクションプランには新規抗菌薬の開発も含まれており、アメリカでは国を挙げて開発を支援した結果、2014年以降FDAで新規承認される抗菌薬が徐々に増加しています*2,3。
日本やそのほかの国でも、アメリカのように製薬会社への経済的支援が進めば、耐性菌に対する新たな抗菌薬開発も期待できるかもしれません。
平井敬二:日本発の抗菌薬開発の歴史と今後の展望について.日本化学療法学会雑誌 68(45):499-509,2020(*2)
アクションプランとは|AMR 臨床リファレンスセンター
Talbot G H,et al.: The infectious diseases society of Americaʼs 10 × ʼ20 initiative (10 New systemic antibacterial agents US Food and Drug Administration approved by 2020): Is 20 × ʼ20 a possibility? Clin Infec Dis 69: 1-11,2019(*3)
推奨される対策
日本の対策アクションプランは2016年4月以降、5カ年ごとに策定されています。前述した新規抗菌薬の開発を含めて、下記の内容が扱われています。
- 普及啓発・教育
- 動向調査・監視
- 感染予防・管理
- 抗微生物剤の適正使用
- 研究開発・創薬
- 国際協力
厚生労働省「薬剤耐性(AMR)アクションプラン 2023-2027(概要)」p.1より引用
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/ap_gaiyou.pdf
なかでも我々医療従事者が主体となって行うべきは、病院内における標準的な感染予防、いわゆるstandard precaution(標準予防策)の徹底と、抗菌薬の適正使用です。
たとえば京都大学病院では、適切な抗菌薬の選択、 投与量と投与期間の適正化、血液培養検査やそのほかの感染症検査(心エコーなど)の実施、抗菌薬のデエスカレーション、診察時の標準予防策の徹底など多方面から介入を行い、黄色ブドウ球菌の耐性率を低下させたことが報告されています*4。
将来、耐性菌による感染症から多くの命を守るためにも、医師としてできる限りの対策を実践しましょう。
まとめ
世界中で問題視されている耐性菌について解説しました。耐性菌のまん延は感染症による死亡者数の増加だけでなく、医療費の高騰による経済の圧迫など、さまざまな問題を引き起こします。普段の診療で何気なく処方している抗菌薬が、その原因の一端かもしれません。
我々医師はこの現状を受け止め、抗菌薬の不適正使用につながり得るすべての感染症を予防し、質の高い診断と感染症の適切な治療を実践していくことが求められています。この記事を契機に、改めて日常診療を見直してみてはいかがでしょうか。